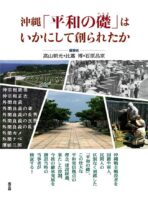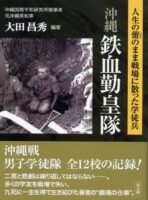兵士 愛知県 日比野勝廣
屍とともに半年

病院を求めて
当時、一分隊長であった私は、沖縄の激戦地「嘉数」付近、「安波茶」の第一線において右腕負傷。人事不省中救助され奇跡的に生きかえった。それ以後、充分手当を受けぬまま、第一線陣地より「小禄医務室」、「南風原陸軍病院」、「南風原陸軍病院糸数分室」と、後から迫る敵を逃れ、病院を求めて次々と後退していった。
その間の苦痛はなみたいていではなく、傷口は腐り、「うじ」がわき、「南風原」に着いてからは遂に、「破傷風」にかかり、九分九厘まで死ぬとまで言われるこの病気に対して、軍医は、冷たい一べつを与えたのみで、一回の診療もしてくれなかった。再起を誓って危地から後退してきた気持ちも無視され、幾日も「けいれん」の続く体をまったく自分の精神力だけで支えていた。食事はもとより水ものめず「はえ」と「のみ」と悪臭のこもるこの病院にも、次第に敵の手がまわり、五月十五日には、「助かる見込みの者だけ後退させる」と命令が出た。もちろん、私は除外組で、置去り組だった。夜半すぎ「沖縄防衛徴集兵」が来て、指名された者だけを次々と担架で運び出していった。全身けいれんで口とからだの自由を失っている私の意識だけが、「この機を逃がしたら助からぬ」と密かにささやき続けた。意を決して、無謀な考えを抱いて時を待っていた。
山の中腹に横穴を作り、中を三段に仕切った棚のいちばん奥の二段目にいた私は、ちょうど下を通りかかった担架目がけて力の限り転げ落ちていった。狭い道路での、この予想外のできごとに、担架で運ぶ者もびっくりしたようであったが、文句を言わず、そのまま外へ運び出して行った。担架を担ぐ老兵に、「助けてくれ」と片手で拝んだ。絶えず艦砲が炸裂して、照明弾で、あたりは昼の如く、しかも、いつ爆弾で四散するかわからぬ中を、老兵はいたわり続けてくれ、明け方近くになって雑木林の一角に穴の入口を発見、この中にかろうじてたどりつくことができた。
穴の中は、トンネルの二倍以上もあろうか、天井から何百何千と数知れぬ鍾乳石のつららが下がり、奥へ向って道路をはさみ両側は、板敷きで間切りされていた。ここは、「島尻郡玉城村糸数部落(現南城市玉城字糸数)にある糸数アブチラガマで、戦時になって、陸軍病院に変わった所である。
傷口にうごめくうじ
この頃、戦の模様は極度に悪化して、すでに、「首里」を放棄していた。しかし、このガマにまでは砲弾は届かなかった。破傷風はいよいよひどく、傷口には「うじ」がうごめき、その痛みはけいれんに加わって、死なないのが不思議に思えるほど体力は弱り果てていた。入院して数日後、「当病院は解散する。個人行動でただちに真壁に行け」と命令された。「来るべき時が来た」と観念した。ちょっとでも歩ける者ははい出して行った。生命を守るに必死の地獄は、ガマの中に繰り広げられた。これが赤裸々な人間の姿であろう。我先にと友をけとばしながら出て行く。この人たちの姿を眺めながらどうすることもできぬ私は、「看護婦さん、看護婦さん」と呼び続け、「うじを取ってくれ」とうなり続けた。隣りで退去準備中の一人は、引きつった私の顔を思いっきり、げんこつでなぐりつけた。気の立ったこの人は私の騒ぎを何と感じたか知らぬが、なぐられた時には、みじめな、情ない自分を意識せずにはおられなかった。
大半が出て行き、静かになったガマの中で、私をゆすぶる一人の看護婦さんがあった。まっ黒になった右手の包帯を丁寧にはがし、ピンセットで「うじ」を一つ一つ取ってくれた。ざくろの割れ目に似た傷口深く喰い入っている「うじ」は汚なく、若い女性でできる仕事でないはずだが、黙々として、彼女は、手を動かした。その横顔の神々しさ「地獄で仏」とは、このことを言うのであろう。学徒動員で働いている現地女学生のこの人は、解散を告げられて、最後の仕事に私を選んでくれたのであろう。明け方近く、一言の言葉も無く静かに立って行った。私に深い慰めのまなざしを残して。
「明日、全員迎えに来るまで、待っておれ」と残して行った軍医の言葉を信じて、百数十名は待ちに待ったが、二日、三日と経っても誰も迎えに来てはくれなかった。死期が刻々と迫るのを感じて、望みを失った者は、次々と自決したり、絶叫を残して死んでいったりした。私も、「地上で野ざらしになるよりはガマの奥深く眠ることをせめてもの幸せ」と考え、一切をあきらめて運命のままにまかせようと覚悟していた。」
吉田君の死
私の横には、末長君(九州出身)、吉田君(東京都出身)、吉田君(長野県出身)と三人寝ていた。痛みにうなされると東京の吉田君が、「静かにしろ」と叱りとばし私をなぐった。体には水分一滴なく、骨と皮だけで死人同様であるにもかかわらず、意識だけ明確で、すぐ下を地下水が流れているのか、水の音が聞えた。それが、頭にこびりついて、「あの水さえ飲めば、死んでも悔なし」と、一途に、思いつめていた。動けぬ体では全く罪な話で、左手で耳をふさいでも右耳から水の音は伝わり、「水、水」と、水のとりこになって気も狂わんばかりであった。今にして思えば、その一念が「生」を保つ支えとなっていたようである。全てを水に集中したことが、結果的に、死神を寄せつけなかったのだろう。こんな時、大声で怒鳴り散らす者はすべて狂っている者で、この世の声とは思えぬうめき声も聞える。声の出る者は、まだ元気のあるほうで、ひっそりといつの間にやら死んでしまう者も多数出た。まっ暗なガマに時々「大こうもり」らしい羽ばたきが静けさを破るほかは、「動」のない「死」の世界が幾日も続いた。
仰向けに寝ている背の下にムズムズしたものを感じ、それらが、やがて首筋、お尻の下にも感じられる。手さぐりでつまんだら、それは、大きな「うじ」で群をなしていた。どこからきたものか、あたりを見まわした時、ふと隣りの吉田君(東京)が、いつの間にか死んでいた。そして、すでに腐り始め、そこからはい出していることが分かる。死臭鼻をつき吐き気さえ感じていたが、まさか一番元気だったこの人が死んでいるとは意外だった。そういえば自分をなぐらなくなっていた。
悪臭と「うじ」に悩まされつつも白骨化していく友の傍らから離れるだけの体力もなく、「今にこの姿になるのか」と恐ろしい戦傑の時が続いた。それでも水を求める私は、手近なところに水のあることを思いついた。「小便を飲もう」私はいっしんに放尿に励んだ。しかし、この妙案も効き目はなかった。小便になるような水分は体の中には残っていない。
地下水に生気をとりもどす
ある日、向う側の上部にある空気穴から黄燐弾が投入され、大音響と共に跳ね飛ばされた。気を失ってしまった。気づくと棚の上から落ちていた。他の者も幾人か吹き飛んだらしい。しばらくしてから、正気に戻り、「ああまだ生きていたか」と辺りを見ると、ここは五メートルばかり下の水たまりの傍らであった。爆風で飛ばされた時、奇跡的に地下水の流れへ運良く行ったものとみえる。私の切望した水が得られたことに、喜びを感ずる暇も惜しく、一気に飲み続けた。痛みも忘れ、とにかく腹いっぱいになるまで飲み続けたことは、今でも覚えている。水腹であっても満腹感は、私に「生命力」を与えてくれたのか、眠りを誘い、起きてはまた、飲みして、少しずつ動くことができるようになった。動けるといっても、「いざる」ことぐらいで、それでも死んだ者の靴下に玄米の入っていることに気づき、早速手にとって、思わず口にほおりこんだが、弱ったからだで玄米が消化されるはずがなかった。それでも根気よく口に含んで無理して飲み下してやった。
他の人たちは、靴、飯ごうなどを両手に捧げ、上を向いて寝ていると、天井からのしずくが時々ポツンと落ちるのを気長に、それを仕事としていた。「自分だけ腹いっぱい飲み生気を得たから、この喜びを皆に」と決心。かつて、水の鬼と化した自己を省みつつ、水筒を首にかけ、手さぐりで十歩いざり、息絶え絶えになって動けなくなり、ひと休みして、またいざりという状態を繰り返し、一日がかりでやっと水筒いっぱいの水をくみ重傷者渡すと、手を合わせ、泣きながらひったくるようにして一気に飲む。「他の著にも分けるように」と言っても、水筒を力限りかかえて離さず、「ありがとう」拝まれると、無理にとりあげることもできない。「水」「水を頼む」と叫びたてられると、体をひきずっても水汲みを続けなければならない。こうして水汲みが日課となり、おかげで少しずつ体力が出てきた。そのうちに恐ろしい破傷風の心配も、「けいれん」の苦痛も体内から消え、体を動かしても苦痛でなくなってきた。自分でも解らぬ力が死神を追い出したのか、奇跡はまたしても私を生へ導いてくれたらしい。
私の与える水を末期の水として故郷を思い、肉親を恋しつつ仏になっていく友を見守って、いつ同じ運命がくるか知れぬのに、「よろしく頼む」と言われれば、手を握り、「うん、きっと……」と遺言を聞くその胸中は、今も忘れることができぬ悲しい思い出である。あの友、この友の最期が、眼の前に浮かんで涙のにじむことも時々あるほど、悲惨な状態であった。
注射液の発見
ある日、ヨロヨロと穴の奥へ歩いていった私は、玄米一袋、缶詰、乾燥味噌、他に注射液多量を発見。鬼の首を取ったように喜び、皆の手に、まず、第一番に配ったのは注射液であった。薬の知識は皆無だが「リンゲル」「カンフル」は重病人に使うぐらいは、分かっていた。注射代りに何本も飲ませてやった。赤字で書いてあるものは、劇薬だと思い、他のものは何でも手当り次第口の中へ流し込んでやった。すると、何となく体に効いていく感じであった。「今少し発見が早ければ助かった人もあったろうに」と思いつつ残念でしかたがなかった。
ほのかなローソクの光の中で、誰一人しゃべらず、黙々として、薬を飲む友の顔を眺めていると、「おれが死んだら仏壇に大きなぼた餅と、丼いっぱいの水を供えてくれよ。お母さん……」と何度も叫びつつ死んでいった友が、ひとしお哀れに思われて、その死体にカンフルを何本も注いでやったりした。
外気にふれる楽しさ
これをきっかけに、私たちは生きんがための共同生活が始まった。入り口をふさがれ、わずかな空気穴だけが外と通じる。ガマ内は、必要以外は明かりもつけず、暗闇の生活で、空気穴から差し込む光で昼夜を知る。レンズを通して熱をとり、玄米のかゆに甘藷の葉を混ぜて飢えをしのぐ大ごちそうとした。
夜になると、やっと、体が抜けるほどの穴からはい出して、甘藷の芋や葉などの食糧を見つけに歩いた。長いガマの中の生活で最も楽しいのは外に出る時で、まだ、危険が去ったわけではないが、毎夜出かけ、夜露にぬれ、雑草にふれ、木々の梢をゆさぶる空気を胸いっぱい吸う、そのうまさは、外気を断たれている者だけが知る喜びであり、全くおいしいと思う。
ガマへ帰る時、野草を採り、歩けぬ者へのおみやげとするのが常であった。この野花や、青葉をいつまでも犬のように嗅いで、まるで緑を吸い取っているようであった。外に出られぬ苦しみを、こうして草花に託す毎日であった。
暗闇が心をおちつける
何ヶ月も暗黒にとざされていると、「太陽を拝んで死にたい」「外で死にたい」と、日光を求め、緑にあこがれ狂ったようになって、大部分が息絶える。残されていく私たちは、ガマの暗さの中に沈みきって、ふたたび「死」について考えるときが多くなった。時折、明かりをつけ、ぼんやりと辺りを照らすと、天井から無数に下る石のつららは、その先にしずくを光らせ、気味悪く私たちに迫ってくる。辺りに転がっている多くの死体と共に、死の世界をまざまざと見せつけられた思いで、非常な恐怖におそわれ、思わず、「ふっ」と明かりを消す。もとの闇にもどると、今みた地獄図が眼に残り頭を抱えこんでしまう。
幼い日、恐怖の時に、母の膝にすがったそのままの心が、大の男にもひそんでいるのだろう。怖い時は、母の幻にすがり、助けを求め、「おかあさん」と、知らぬ間に心の奥底から叫んでしまうことがたびたびあった。
このガマの中は、全くの闇であったことが、かえって私たちを狂わせずに、少しでも落着かせていたのではないだろうか。ガマの様子をまともに見ていては、すでにそれだけで悶絶していたことと思う。日本の敗れたことを知らず、「今に援軍が来る。その時は……」と再起することのみを思い、耐乏の毎日を続ける。その間には、お互いに生きんがために、色々なトラブルもあったが、原始的で最低生活を維持するために、様々な工夫をこらしていった。マッチがなくなれば、よもぎを干して縄にし、レンズで火種をとる。ただ、湿気が多いのには閉口した。
敗戦を疑いながらガマを出る決心をする
やがて、最後まで体力を保ち続けることのできたわずかな者だけの勝利の日が、来た。秋風の吹く季節になって、遂に、発見されたのである。
数名の日本兵が、突然、抜け穴から入ってきて、一同を驚かせた。さらに、その言葉に我々は呆然とした。「日本は戦争をやめた。兵隊は、全部、家へ帰ることができる」と言った。いも畑に残された足跡から、ここを発見し、呼びに来たと言うが、「そのようなばかげたことは、絶対ない」と一同は、頑として信じない。「一度、外に出て話を聞け」と詰め寄られ、思案の末、私が代表として単身、様子を見に行くことに決定した。間違って捕虜になった場合にはと、手榴弾を二個ふところに隠し、この人達の後からガマを出た。その時の気持ちは、決死の覚悟であった。これまでの苦労が水の泡に帰すかもしれぬと、危機感さえ感じた。
幾月ぶりかで、昼間青空の下に立ってみて、ギラギラ光る太陽を仰ぎ、緑なす山々を眺めたとき、それは、初めてカラー映画を見たときよりも美しく、鮮かさには感嘆の声も出ず、ただ目をみはるばかりであった。自然の緑が、これほどまでに印象的であったのは、生涯でこの時だけであろう。ここに至っては、どのような条件下でも良い。死ぬまでこの光の中で生きたいと、一刻も早く、ガマから出たくなり、早速引き返し一同に伝えた。通訳を通して、「皆、揃って出ます」と、直ちに、狭い入り口から光の中に、出ていった。長い光のない生活からようやく解放されたよろこびは、その後に、どのような事態が待ち受けようと問題ではなく、青白くふやけた顔のどれにも一度に生気が溢れていた。最後に歩けぬ者を背負ってガマをはい出す時の私は、感無量の涙があふれて止めようもなかった。ここに運ばれてきた時のことが、つい昨日のように思われ、「人を助けて出る」という幸せを、心より感謝せずにはおられなかった。
繰り返したくない悲惨な戦い
出揃った一同は、何の危害も加えられず、待っていた自動車に分乗し、それぞれ収容所に向った。それから二十年余経った今日。あの日、「何のため今まで苦しんできたのか」と反問する時もなく、あっけない別れ別れになってしまった。その後、住所も分からず、再会の機会をみつけることもなく過ぎてきた。しかし、苦しみ通したガマの生活を、一日として忘れたことはない。ガマのつららとともに、幾多の戦友の面影が、脳裏に焼きついている。肉体に残る傷跡を見るたびに、これからも決して、私から離れることはないだろう。
科学万能の時代に、その粋をもってしても屈せず、破壊を厳として拒んだ万古不変のあのガマ、自然の威厳。この威厳は、いつまでも続くだろう。偉大なる自然は、「弱い人間」の味方として戦いから守ってくれた。半月以上、毎日爆雷を投げ込み、穴の口を完封したガマに、よもや重傷の身を捨てられ、半年以上も生き延びていたなぞとは、自然の偉大な働きとしてしか判断のつきかねることである。
幸い、私は奇跡的に生還でき、苦しかった当時を想い出して綴ることが許されているが、幾多の友の中には、私以上に苦しみ、ただ一人見知らぬ土地で、寂しく息絶えていった。戦は、勝っても負けても悲惨である。死者に声があれば、私と同じことを叫び続けるであろう。「生」から見離され、しかし、生命のある限り生きてゆかねばならなかった人間。「生きる」苦しみは、とうてい言葉では表わせるものではない。私のつたない綴りの中にある事実は、すべて遠く過ぎ去った悲劇であるが、今もって、沖縄のガマの奥深く、永久に発見されるすべもなく眠っている「みたま」の幾多あることを思うと「日本国民すべての人が、もういちど悲惨な戦争を想起してほしい」みたまに代って、私は叫ばずにはおられない。